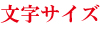
|
 |
 歴史 〜history〜 歴史 〜history〜 |
萩焼の歴史
萩焼の起源は約400年前(1604年)になります。
豊臣秀吉の文禄・慶長の役(1592〜1598年)で
朝鮮人陶工の李勺光(り しゃくこう)と李敬(り けい)が日本に連れて来られました。後に、毛利輝元(もうり てるもと)が広島で二人を預かっていましたが、
1600年の関ヶ原の戦いに敗れた毛利輝元は領地を今の中国地方5県から山口県だけに減らされ、城を萩の地に移すことになりました。これとともに二人の兄弟も萩に住まわせました。
李勺光には山村(やまむら)、李敬には坂(さか)という名字が毛利氏から与えられました。
李勺光は今の萩市椿東中の倉(はぎちんとうなかのくら)で薪の使用を許され、
松本御用窯(まつもとごようがま)として窯を開いたのが萩焼の始まりと言われています。
よって萩焼の当初は朝鮮半島の高麗茶碗(こうらいちゃわん)に似て、作り方も形も同じでした。李勺光の死後、弟・李敬が後を継ぎ「坂 高麗左衛門」(さか こうらいざえもん)に任せられました。
|
 慶安時代(1648年)に入ると多くの諸窯(しょがま)が毛利輝元の家来として雇(やと)われ、古萩の全盛時代を作ります。(坂家の三代までを古萩といい、萩焼の黄金時代という。)
しかし、寛文(1661年)以降はそれまでの高麗茶碗や織部(おりべ)、御手本風以外に楽焼の作風が加わり萩焼独特のものが焼成されました。昭和になって三輪休雪(みわきゅうせつ)、のちに休和(きゅうわ)が弟、のちに休雪(きゅうせつ)から壽雪(じゅせつ)と一緒に休雪白(きゅうせつしろ)という独特の作風を作るなどして萩焼をまた盛んにしました。
慶安時代(1648年)に入ると多くの諸窯(しょがま)が毛利輝元の家来として雇(やと)われ、古萩の全盛時代を作ります。(坂家の三代までを古萩といい、萩焼の黄金時代という。)
しかし、寛文(1661年)以降はそれまでの高麗茶碗や織部(おりべ)、御手本風以外に楽焼の作風が加わり萩焼独特のものが焼成されました。昭和になって三輪休雪(みわきゅうせつ)、のちに休和(きゅうわ)が弟、のちに休雪(きゅうせつ)から壽雪(じゅせつ)と一緒に休雪白(きゅうせつしろ)という独特の作風を作るなどして萩焼をまた盛んにしました。 |
一楽 二萩 三唐津(いちらく にはぎ さんからつ)
いつの時代から言われだしたかわかりませんが、「一楽 二萩 三唐津」と呼ばれるようになりました。これは茶の湯の好みだそうで、茶の湯において茶人に愛されるすぐれた、お茶を飲むときに使う陶器を呼ぶ表現です。
それぞれ、京都の楽焼(らくやき)、山口の萩焼(はぎやき)、北九州の唐津焼(からつやき)を指します。
いずれも優れた焼き物ですが、それぞれの特徴があり、その良さに順位をつけたものを「一楽 二萩 三唐津」と言われているようです。ですが、これはあくまで「感じ」であって焼き物の良し悪しを数値化したような基準があるわけではありません。萩焼の良し悪しは使う人それぞれによって異なります。その良さを見つけて感じるのも焼物の良さかもしれません。 |
萩の七化け
 萩焼は長く使いこむうちに味が出てくるといわれています。 萩焼は長く使いこむうちに味が出てくるといわれています。
萩焼は吸水性がよく、焼きあげると釉薬(ゆうやく)の表面に細かいひびが入ります。(これを貫入(かんにゅう)という。)このことからお茶やお酒などが萩焼にしみ込んで色が変わります。使い始めたときの色合いと使い込んだときの色合いとでは
器の印象もかなり異なり、このような色合いの変化を「萩の七化け」といいます。
萩焼は、その半分以上は使う方が作る焼物と言われます。
萩焼でお茶を飲み、貫入に茶渋などが詰まって漏れを防ぐこと。
また使い込むことで色合いに変化がおこることが
萩焼の楽しみ方であり、また最大の特徴でもあります。
|
 |



 慶安時代(1648年)に入ると多くの諸窯(しょがま)が毛利輝元の家来として雇(やと)われ、古萩の全盛時代を作ります。(坂家の三代までを古萩といい、萩焼の黄金時代という。)
しかし、寛文(1661年)以降はそれまでの高麗茶碗や織部(おりべ)、御手本風以外に楽焼の作風が加わり萩焼独特のものが焼成されました。昭和になって三輪休雪(みわきゅうせつ)、のちに休和(きゅうわ)が弟、のちに休雪(きゅうせつ)から壽雪(じゅせつ)と一緒に休雪白(きゅうせつしろ)という独特の作風を作るなどして萩焼をまた盛んにしました。
慶安時代(1648年)に入ると多くの諸窯(しょがま)が毛利輝元の家来として雇(やと)われ、古萩の全盛時代を作ります。(坂家の三代までを古萩といい、萩焼の黄金時代という。)
しかし、寛文(1661年)以降はそれまでの高麗茶碗や織部(おりべ)、御手本風以外に楽焼の作風が加わり萩焼独特のものが焼成されました。昭和になって三輪休雪(みわきゅうせつ)、のちに休和(きゅうわ)が弟、のちに休雪(きゅうせつ)から壽雪(じゅせつ)と一緒に休雪白(きゅうせつしろ)という独特の作風を作るなどして萩焼をまた盛んにしました。
 萩焼は長く使いこむうちに味が出てくるといわれています。
萩焼は長く使いこむうちに味が出てくるといわれています。 